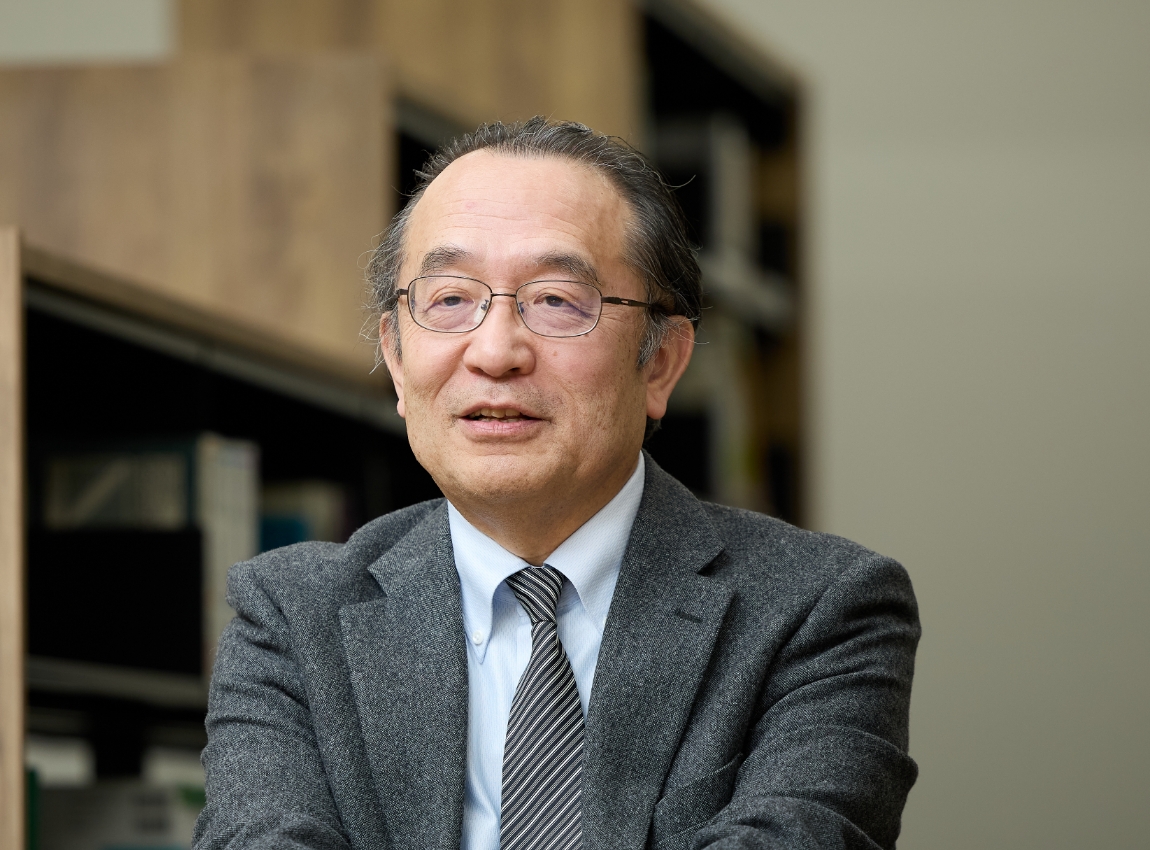教育分野担当教授
森脇 健夫
臨床教育学で扱う事象は「日常の辺々」に存在します。「神は細部に宿る」が私の研究・教育のモットーです。
- プロフィールについて教えてください。
- 生まれは千葉市なのですが、全国を転々としてきました。鹿児島で10年、東京で10年暮らしたことがあります。現在は京都府の木津川市在住。
- 長らく三重大学に勤めていました(30年間)。教育学部の教員として教員養成、教職大学院で現職教員の再教育にかかわってきました。
- コロナ禍を経て2022年度からこちらの大学院でお世話になって4年目です。教師だけではなく、保育士、看護師、保健師、いろいろな仕事をされている社会人院生と一緒に研究をすることは私にとってとても刺激的で楽しい時間を過ごしています。
- 研究内容について教えてください。
- 3つあります。1つ目は授業づくり・授業研究です。もともと教育方法学を専攻していて教育内容・教材論を研究していたのですが、最近では、めあて・ふりかえりに焦点をあて、その改善を中心に授業づくりを考えています。「教えて、ともに考え合い、そして学習者を育てる」授業を目指しています。
- 2つ目は、1つ目とも関係するのですが、対話的事例シナリオづくりをもとにしたPBL教育の研究をしています。最近、本を出しました。山田他著『PBL事例シナリオ教育で対人援助専門職を育てる』三恵社2025.3です。興味のある方は手に取ってご覧ください。
- 3つ目は、教師のライフヒストリー研究です。ライフヒストリーと言っても教師の人生全体を対象とするのではなく、専門職として必要な資質・能力がどのように形成されてきたのか、をインタビューや実践記録を通して理解しようとする研究です。最近は、日本語教師(国内外)のライフヒストリーにも興味関心を持っています。
- なぜその研究が社会にとって必要なのかを教えて下さい。
- 臨床教育学が誕生したのは、広い意味での教育現場で起こっている問題への取り組みの必要性からだと思います。
- 従来の学問や理論では対処しきれない性格を持っている問題群です。例えば家庭での「児童虐待」、また学校での「いじめ」「不登校」「学級崩壊」そして対人援助職の現場で起こっている「早期離職」「人間関係の構築困難」等です。
- こうした問題を臨床的に解決することを課題とする教育学が必要だというところから臨床教育学が生まれました。「現場に寄り添う」「理論と実践の往還関係」「学際性」「臨床の知」がキーワードです。
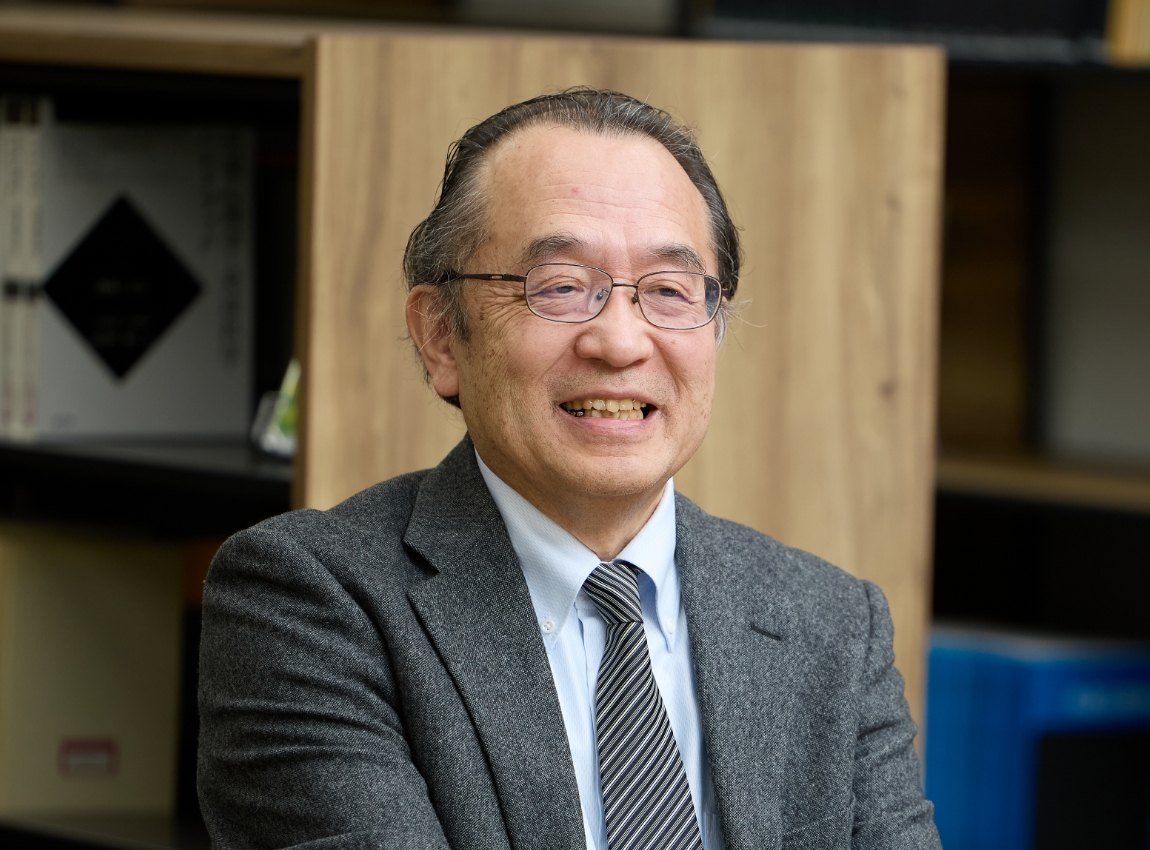

- ご担当の科目の臨床教育学の中での役割を教えて下さい。
- 臨床教育学総論、臨床教育学特論、臨床教育学総合演習と、いわば、臨床教育学の「看板科目」を担当しています。総論では、臨床教育学が何を契機に誕生したのか、どういう守備範囲を持っているのか、方法論の特徴は、といったことを扱っています。
- ゼミ運営の特長として意識されていることはありますか。
- 私のゼミでは、博士課程、修士課程を問わず合同でゼミをしています。それは、お互いの切磋琢磨の中で論文を書き上げてもらいたいからです。徒弟制的な1:1の局面も必要だと思いますが、ピアな関係性や「ななめうえした」の関係の中でこそ当事者感覚(sense of agency)が保持できると考えています。博士、修士を問わず「お互いの研究に関心を持ち合い、援助しあう精神を持っている」のが私のゼミの特長です。
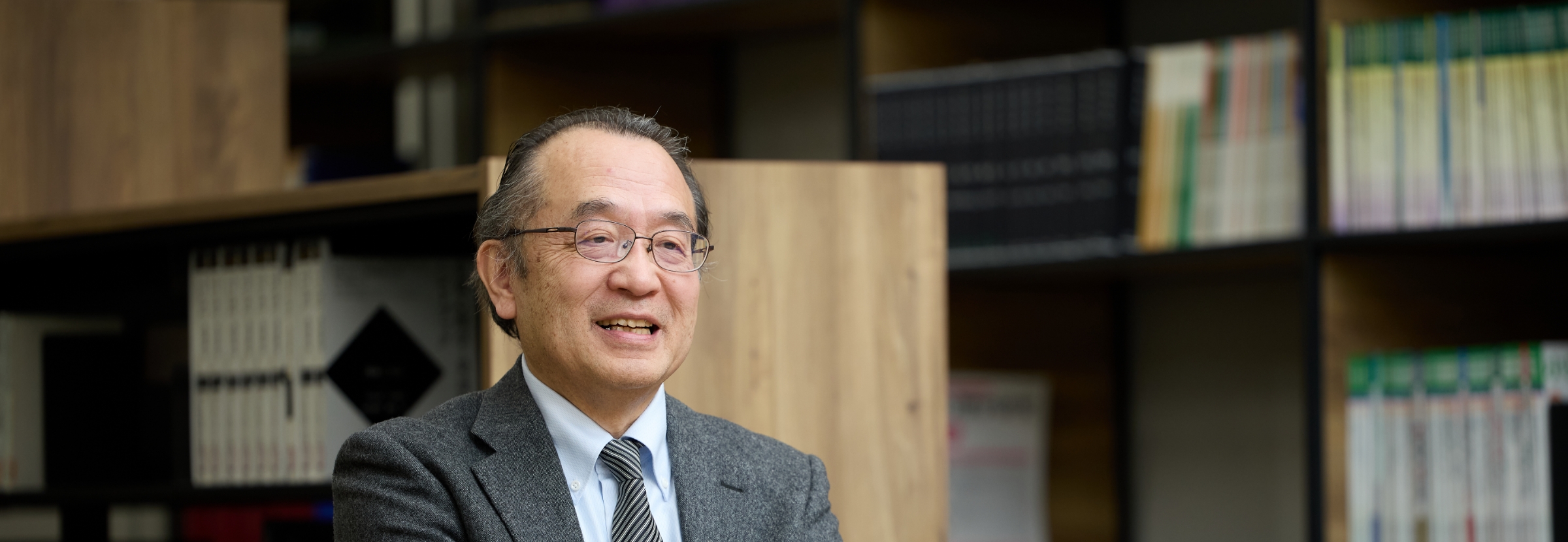
- どんな経験や関心をもつ学生に進学してほしいですか。
- どんな経験でもいいと思います。ただ、経験から少し離れて(日常性という「荷物」をいったん降ろして)ふりかえってみようということをふと思い立った人は誰でも歓迎です。
- これから受験しようとする方へメッセージをお願いします。
- 日常性の中に埋没してしまっている自分にふと気づいたとき、自分のやってきたことの意味や意義を問い直してみたいと思ったとき、その機会(空間、場所、教員や仲間どうしの人間関係)を持てるのが本学の臨床教育学研究科です。昼間の仕事をしながら研究できます。男女共学です。
- まずはぜひ(無料で)授業を見学してみませんか。