
教育分野担当教授
安東 由則 (研究科長)
「人間だもの」のしんどさと喜び。
- プロフィールについて教えてください。
- 学部では、文化人類学を専攻しておりました。フィールドワークに行くことは難しかったので、主として洋書や和書の文献を読むのが勉強でした。当時、日本では山口昌男さんや中沢新一さんらが登場して、脚光を浴びた時期でしたし、吹田の万博跡地に国立民族博物館ができたのも私が大学に入学する少し前であったかと思います。その後、私の関心が明治以降の日本社会に向いたこともあり、大学院では教育社会学を専攻することにしました。
- 近代化に際して、誰が、どのような基準で、どこの国から、何を得ようとしたのか、それを日本社会に受け入れる際、どのような困難があり、それをどう乗り越えたのかを明らかにしたと思っていたのですが、当時の私の力ではとうてい太刀打ちできず、悶々とするうちに大学院生活が終わってしまいます。幸い、山口県の短大に職を得て、そこでもう一度研究テーマを探ることになりました。どうにか研究テーマも定まり軌道に乗りかけたところ、故郷の兵庫県にある武庫川女子大学への就職の話があり、1998年にやってきた次第です。四半世紀が過ぎてしまいました。
- 研究内容について教えてください。
- 教育研究所は、大学教育に関する研究、武庫川学院の教育に関する研究を行う部署であり、私はその所属となりました。既に教育研究所を基盤とする臨床教育学研究科は存在しましたが、私の主な職務は、研究科での研究指導ではなく、大学教育を主たる対象とする調査研究でしたので、本学大学・短大生への教育環境に関する調査・分析を行いました。また臨床教育学研究科と表裏一体ということで、夜間大学院や“臨床教育学”に関する調査研究も並行して進め、その頃から研究科で研究指導をするようになります。
- 院生指導は始まったものの、研究所の大学教育研究は私の職務であり、継続していきました。日本の女子大学に関するデータ収集と分析、女子大学の存立意義に関する学長らへのインタビュー、さらに先進国で女子大学が存在するアメリカや韓国との比較研究へと進んでいきます。近年は、アメリカの女子大学調査を期に、女子大学へのトランスジェンダー女性の入学、支援に関する研究に取り組んでいます。いわゆる“臨床”研究の専門家ではありませんが、研究科に在籍された各分野の先生方から、さらには40名を超えるゼミ生や在籍した院生から、直接・間接に多くを学ばせていただきました。
- なぜその研究が社会にとって必要なのかを教えて下さい。
- 社会学は“社会”(この内容は多様で、文化や歴史、技術なども含みます)というものを想定し、人間と“社会”との関係のあり方、影響関係を手掛かりに考察を進めていく学問です。“社会”はいつの間にか私たちの内部に入り込んでいます(差別意識やジェンダー意識、あるいは“常識”などとして)。また、私たちの外側にあって、私たちの行動や思考を制限する、方向付けてもいます(規範や制度、伝統、風景、土地柄なども)。ある場に生じた問題を真に理解するには、それを根底から解決するには、こうした多重な“社会”を想定し、人間との関係のあり方を捉える必要が不可欠なのです。
- なぜ今日、アメリカであのようなことが起こっているのか?渦中の人物だけを研究したところであの現象は理解できません。その理解には、歴史、宗教、民族、産業構造、地域特性、政治構造、社会階級など多様で重層的な“社会”を分析し、総合的に考察して、解決のための処方を議論するしかないでしょう。生じた現象の捉え方、分析し理解する方法を学んでもらえれば…。
(私の個人研究と大学院での授業は全くの無関係ではありませんが、基本的には切り離して考え、取り組んでいることを述べておきます。)


- ご担当の科目の臨床教育学の中での役割を教えて下さい。
- 本研究科は、教育社会学者である新堀通也先生の「臨床教育学」の構想から実現したものであり、とりわけ、社会病理学・教育病理学を学問的基盤として構築されています。ある場所で問題や課題が生じた際、当事者の心理状態、当事者間の関係、その状況などを詳細に分析していくことが基本ですが、その問題解決には教育学や心理学のみならず、より広範な社会的枠組みの中での解釈と理解が不可欠です。また、その解決には迅速で短期での対応だけでなく、様々な社会的資源を活用し継続して行う中長期的な取り組みや環境整備も重要です。
- 社会学は教育学にも福祉学にも関連する領域になりますが、直接的な対応というよりもむしろ、時代的・社会的見地から多角的に問題を捉え、分析して理解し、中長期的な視点から問題の解決を図るという点に強みがあると考えます。これは社会学全般に当てはま巣ことではなく、私個人の見解です。
- ゼミ運営の特長として意識されていることはありますか。
- ほとんどが社会人の大学院生ですから、各人の職場で、あるいは日常生活の中で生じる何らかの問題や課題をもって入学してこられています。よってゼミでは、基本的に本人の問題関心を大切にしており、指導者の学問領域に近づけるということはありません。そのためか、私のゼミに入ってこられるのは、看護師、教員(高校、大学、専門学校)、保育士、福祉関連など多様な職種の方です。
- 修士論文作成に当たっては、個々で調査を行ない、その結果を分析してまとめることにしています。それぞれの問題関心を活かしながらも、調査の実施可能性などを考慮して、研究目的や調査計画の再設定、分析方法の検討を指導しています。同時に、それぞれの問題関心を、異領域を含むできるだけ広い文脈から検討し、問題関心を焦点化していけるよう指導しているつもりです(修了生がそう捉えてくれておればよいのですが)。修了後、一人でも研究を続けられるよう、確実に一人でも遂行できる調査研究方法を身につけてくれればと思っています。
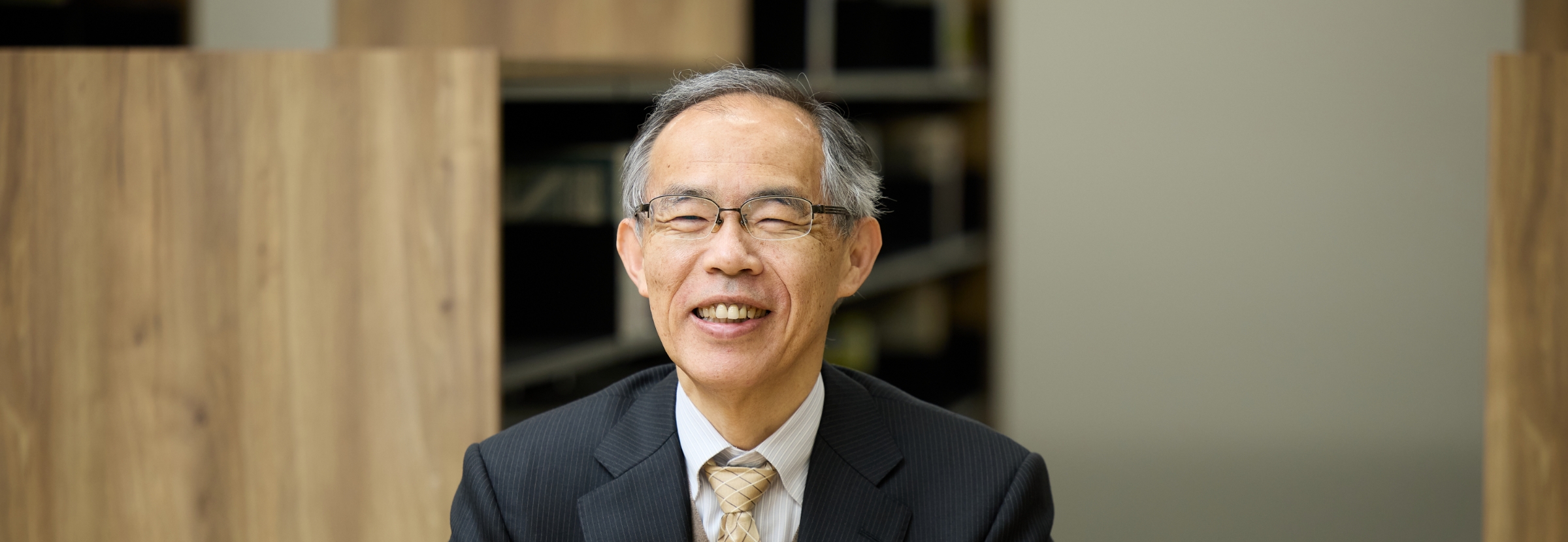
- どんな経験や関心をもつ学生に進学してほしいですか。
- 特にこれはといったものはありませんが、できるならば具体的な問題や課題をもっておられる方、さらに自分一人で取り組もうとするのではなく、周囲の他者と協力しながら、問題に解決に取り組もうとされている方と言えばよいでしょうか。
- 私はこれといった専門領域をもってはおりませんので、一緒に勉強しながら、あるいは教えてもらいながらともに、研究を進めていくということになります。これは、専門領域をさらに深めるというよりも、その領域に囚われることはなく多様で異なる観点から見つめ直し、問い直すことができるかと思います。一つの見方に凝り固まらないで、柔軟に考えていければいいですね。
- これから受験しようとする方へメッセージをお願いします。
- 大学院に進学するには、何かと覚悟がいりますね。職務との関係、家庭のこと、経済面の負担、さらに学習についていけるか、どのような人が入学してくるのか、修士論文を書き上げられるのだろうかなどなど。心配しすぎると、前に進むことはできません。
- これまで多くの社会人院生を見てきましたが、領域を超えた様々な社会人の仲間との出会いがあり、それが刺激になったとの話はよく聞きますし、修了後も交流している方はたくさんおります。また、自分とは異なる領域の教員との出会いもまた、新たな刺激をもたらしているかと思います。皆様には是非とも、実践の場と研究の橋渡し役になってもらいたいと願っています。
- 「叩けよさらば開かれん」。一歩踏み出す勇気をもってください。これまでとは異なった世界が見えてくるかもしれません。

